 |
 |
 |
|
| 龍 | |||
| りゅう・りょう・たつ | |||
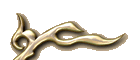 |
 |
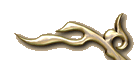 |
|||
|
|
|||||
文責 :
真鶴
|

 |
 |
 |
|
| 龍 | |||
| りゅう・りょう・たつ | |||
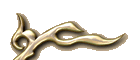 |
 |
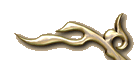 |
|||
|
|
|||||
文責 :
真鶴
|
